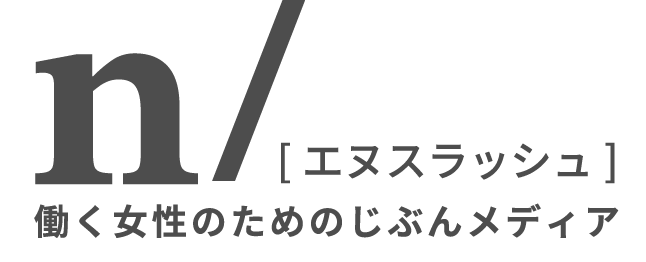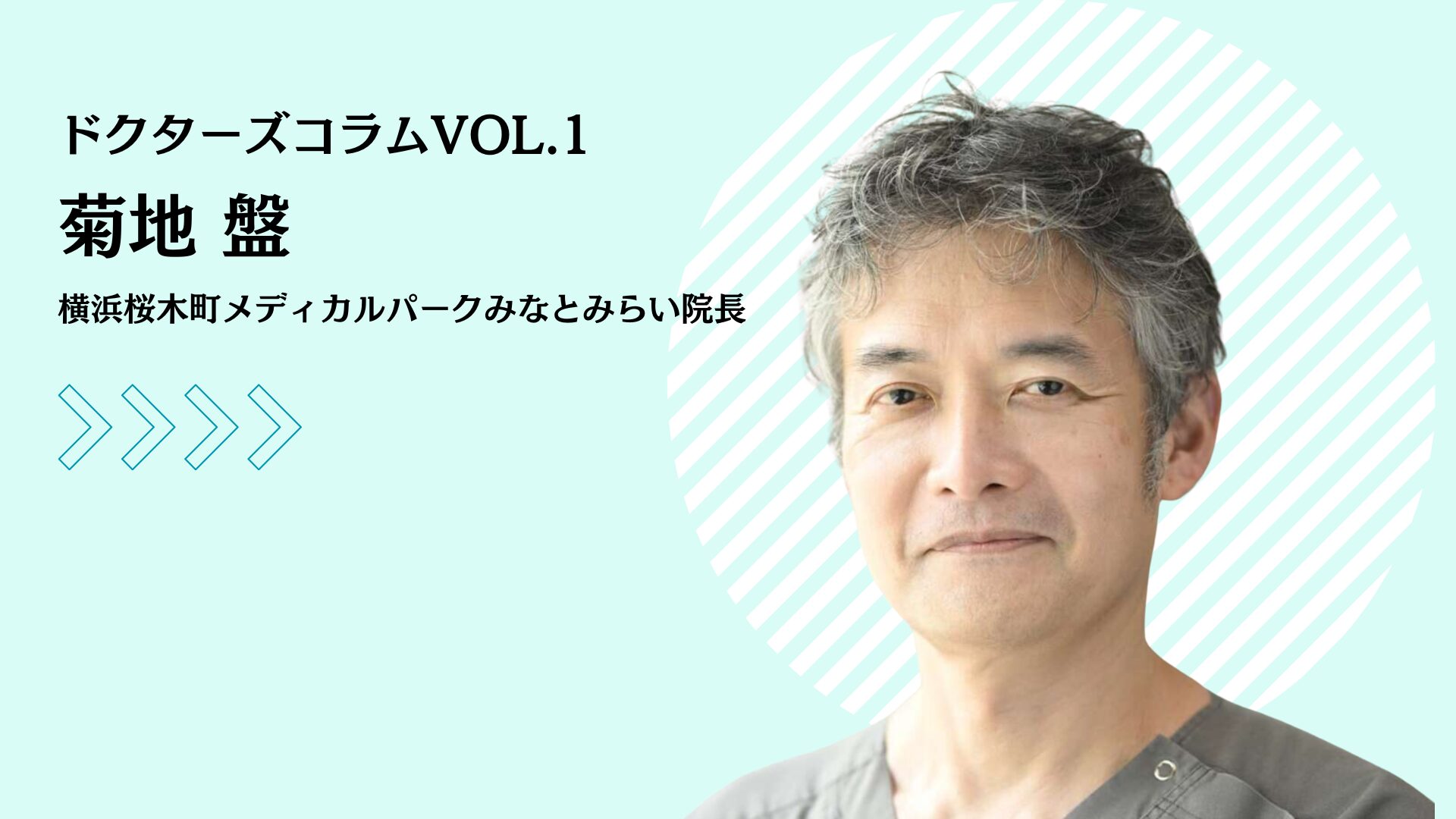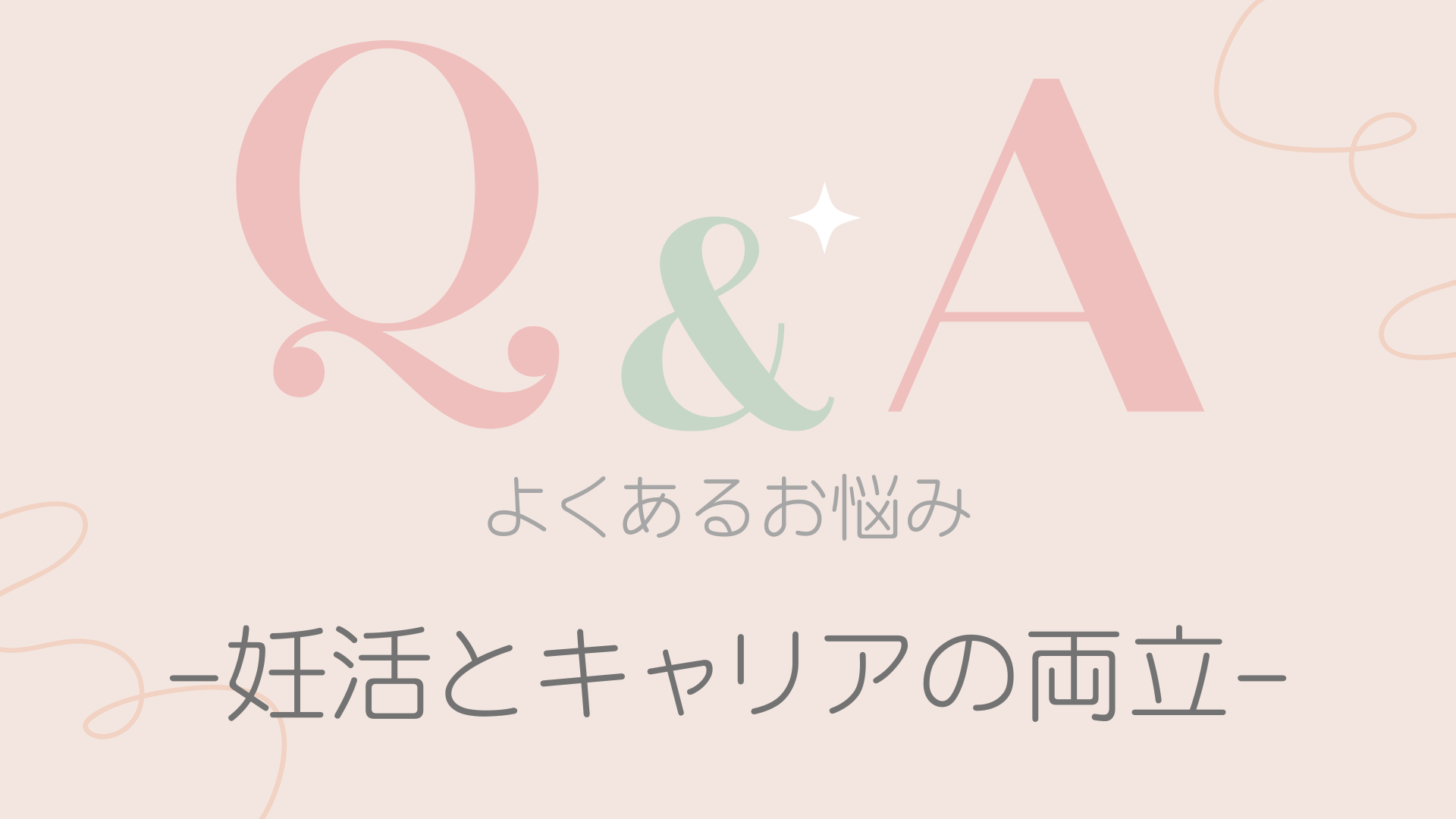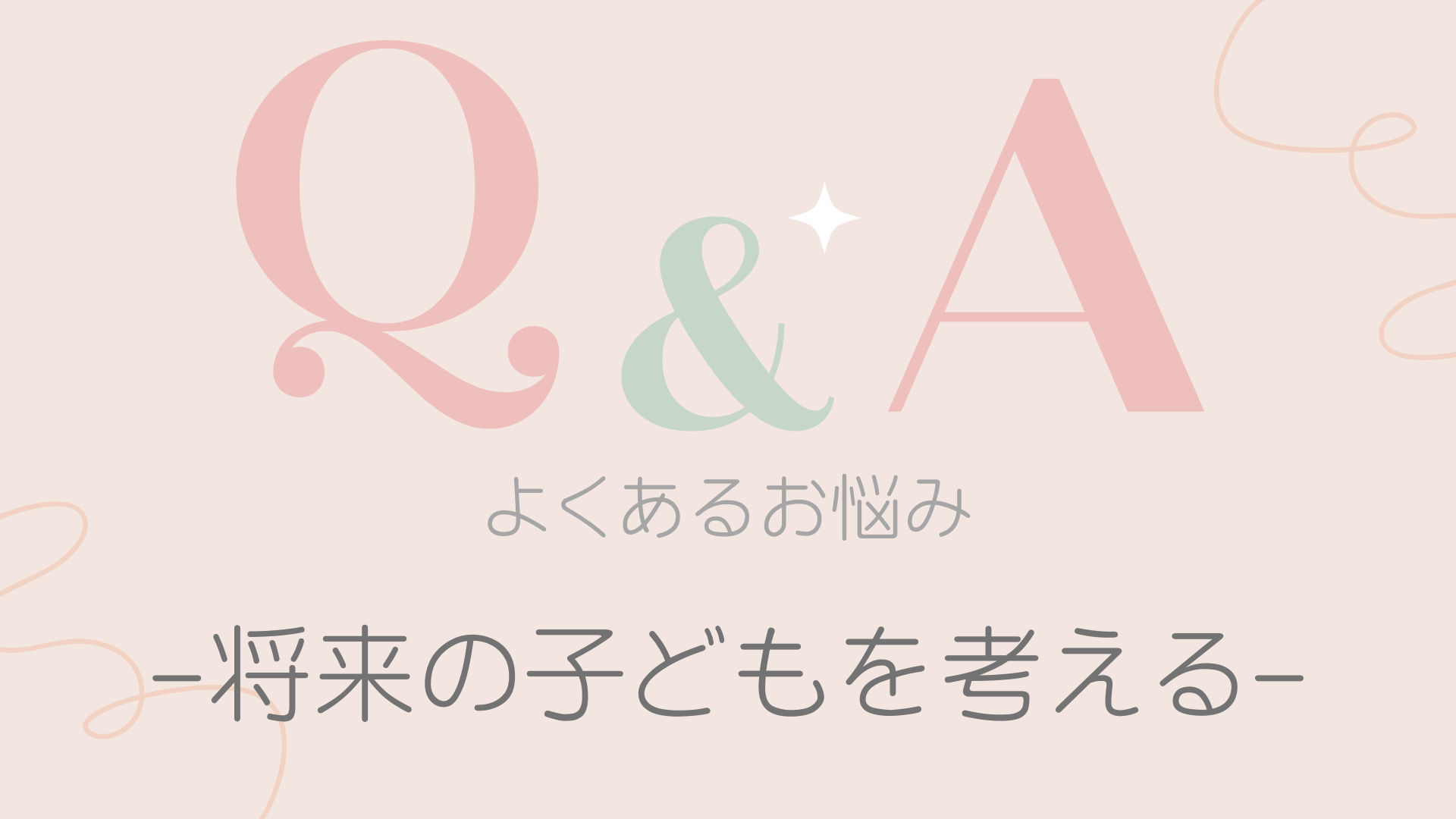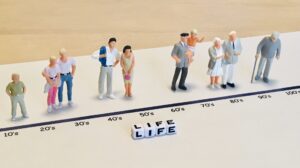n/(エヌスラッシュ)は、「選択肢を早めに、やわらかく」を合言葉に立ち上がったプレコンセプション・メディア。第1回目のインタビューは、不妊治療・妊孕性温存の最前線で診療・教育・啓発に取り組む医師、菊地盤(きくち・いわほ)先生にお話を伺いました。不妊治療を考えたことがある人にも、まだ遠いと感じている人にも、「こんな医師がいるなら安心できる」と思ってもらえる、確かな言葉とまなざしがありました。

森陽菜(以下、森):
本日はお時間いただきありがとうございます。まず、菊地先生のご経歴について教えてください。
菊地盤(以下、菊地):
現在はメディカルパークみなとみらいの院長として、一般不妊治療・体外受精のほか、がん患者さんへの妊孕性温存治療や卵子凍結なども行っています。教育の分野では順天堂大学で非常勤講師として学生教育に関わっており、不妊カウンセラーや医師向けの講習会にも携わっています。
森:
すごく幅広くご活躍されているんですね。
菊地:
“今の治療”と“未来のための医療”の両方に関わっている、という感覚はありますね。特に卵子凍結や妊孕性温存医療は、「将来どうなるかわからないけど、今の私の選択肢を残したい」という方にとって、とても大切な手段。未来のための選択肢が、“今の自分”を支えることもあるんです。
やめ時は人それぞれ。だから納得してほしい
森:
不妊治療を始めた方からは、「どこまで続ければいいかわからない」「やめ時が決められない」といった声もよく聞きます。
菊地:
とてもよくわかります。不妊治療は“出口の見えづらいトンネル”のようなもの。でも私は、「結果が出るかどうか」ではなく、「自分たちが納得できるかどうか」を重視しています。
森:
先生の診療でも、そういった“納得”を支える場面が多いですか?
菊地:
はい。「何回チャレンジしてもダメだったら…」という不安も当然あります。でも、そこで大事なのは、“自分たちで選んだ”という感覚。医師としても、情報を一方的に与えるだけでなく、「一緒に考える」ことを大切にしています。
産婦人科は“とりあえず行ってみる”でいい
森:
不妊治療の入り口に立っている方や、まだ少し先の話かな…と思っている方も多いと思います。そんな方へ、初診の心構えってありますか?
菊地:
実は、あまり身構えなくていいんです。「検査だけでもしてみようかな」とか「今の自分の状態を知っておこうかな」とか、それくらいの気持ちで大丈夫。今は妊活の“情報洪水”のような状態なので、ネットだけを見て不安になるより、医療者に一度聞いてみるのが一番です。
森:
たしかに、“行く前に不安になる”という声も多いです。
菊地:
その気持ちもすごくよくわかります。でも、情報に振り回されすぎずに「今の自分の状態を知る」ことから始めてみてほしいですね。それだけでも、未来の選択肢の幅が広がります。
医療は、人生の可能性を支える技術
森:
卵子凍結などの“将来の選択肢”についての相談も、増えている印象ですか?
菊地:
はい、明らかに増えています。以前は「病気がある方のための医療」という認識が強かったのですが、今では「健康だけど、自分の将来のために保存したい」というニーズが高まっています。社会の変化や、ライフプランの多様化が背景にあると思います。
森:
「今の私」と「未来の私」を同時に支える医療になってきているんですね。
菊地:
まさに!医療というのは、病気を治すだけでなく、“人生の可能性”を支える技術でもあるんです。
知っているだけで、未来の選択肢が変わる
森:
最後に、n/の読者へメッセージをお願いできますか?
菊地:
「将来、子どもを持つかどうかはわからないけど…」という方こそ、知っておいてほしい情報がたくさんあります。医療には「今できること」と「時間の経過とともに難しくなること」がある。だからこそ、選択肢を“早めに”“やわらかく”持っておくことが大切です。知らないまま時間が過ぎて、後から「知っていれば…」と思ってしまうのは、とても悔しいですよね。
森:
本当にそうですね…。
菊地:
人生に正解はありません。でも、“納得できる選択”をするためには、まず「知る」ことから始まります。n/がそのきっかけになってくれたら、医療者としてとても嬉しいです。
編集後記
「未来のために医療に行く」のではなく、「いまの自分を守るために行ってもいい」。
その言葉に、心がすっと軽くなった気がします。“選択肢”というと、どこか「決断しなければ」というプレッシャーもついてきがちだけれど、菊地先生の言葉はいつも、「あなたの今を大切にしていいんだよ」と伝えてくれるようでした。
菊地盤 先生のクリニック紹介
メディカルパークみなとみらい