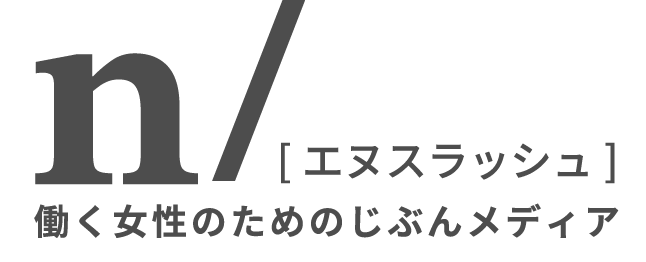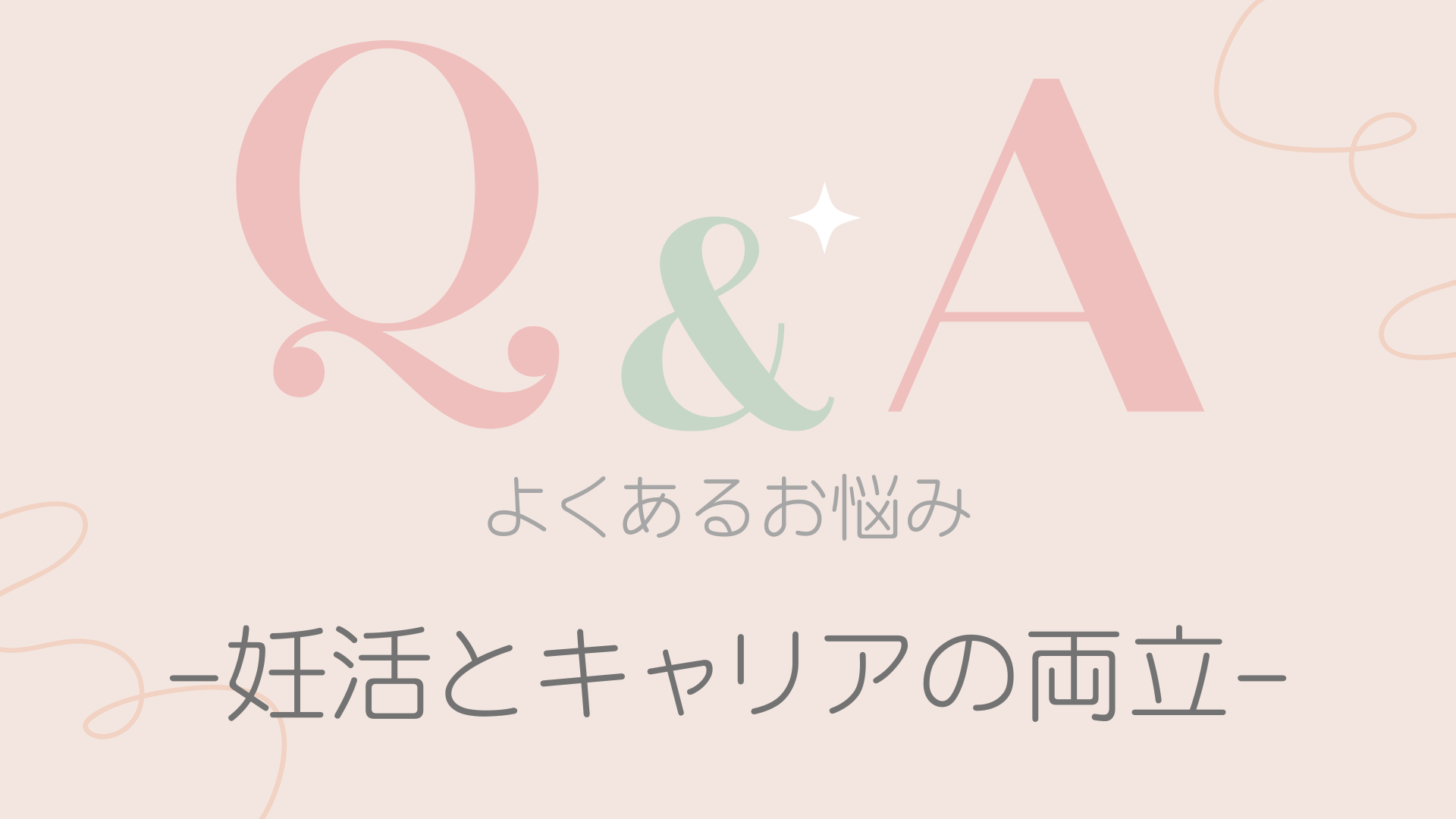2025年8月29日、厚生労働省の専門家会議において、ついに緊急避妊薬のOTC化(市販化)が承認されました。承認にあたり長い間、多くの方が動いてくださいました。処方箋がなくても薬局で購入できるようになるという制度変更は、一見、制度上の「緩和」に見えるかもしれません。しかしそれは、単なる利便性の問題ではありません。今回の決定は、社会が一歩、個人の意思と選択の尊重に向けて進んだことを意味しています。
プレコンセプションとは、「将来を考えるきっかけ」をつくること
私たちn/は、妊娠・出産を前提としない、「プレコンセプションケア(Preconception Care)」の視点から、人生と健康を主体的に捉える姿勢を発信してきました。プレコンセプションとは、将来のライフプランや自分の体のことを、いまの自分のまなざしで見つめてみるということ。
それは、「妊娠する/しない」「子どもを持つ/持たない」にかかわらず、すべての人にとって等しく重要な“自分自身との対話”です。緊急避妊薬のOTC化は、その選択肢のひとつを、ようやく“手の届く場所”に置くことができるようになったということ。
これは、「性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」の基本に通じるものであり、自己決定権の社会的保障への第一歩といえるでしょう。

見えてきたのは「自由」だけでなく、「格差」でもある
一方で、私はこの変化がすべての人に等しく恩恵をもたらすとは限らないことも認識しています。現在、緊急避妊薬は7,000〜9,000円と高額で、誰もが気軽にアクセスできる価格ではありません。また、対応可能な薬局の偏在や、薬剤師の体制・トレーニングの質、プライバシーへの配慮、ジェンダーバイアスにさらされることの不安など、「選択肢はあっても、それを本当に選べるかどうか」は別の問題です。
選択肢があることと、それが実質的に選べることのあいだには、常に構造的な壁があります。その壁を少しずつ崩していくためには、制度設計だけでなく、正しい情報へのアクセスと感情的な安心の確保が不可欠です。
社会全体で「知ること」「話すこと」「備えること」を当たり前に
プレコンセプションの視点は、こうした「選ぶ前の準備」に光を当てます。
それは、“妊娠するかどうか”を決める以前に、もっと早くから、自分の体や心、人生設計について考える機会を持つことを意味します。
今回のOTC化が、そのような前向きな「備え」の文化を社会に根づかせるきっかけとなれば、これ以上嬉しいことはありません。
そして、誰かの選択を批判するのではなく、その背景を理解し、支え合える社会こそが、次の世代にバトンを渡すにふさわしい成熟した社会だと、私は信じています。
わたしたちn/は、プレコンセプションという考え方を通じて、人生のどのタイミングでも、自分を大切にできる人を増やしていきたいと願っています。
【参考資料】
日本産科婦人科学会 平成28年9月 “緊急避妊法の適正使用に関する指針”